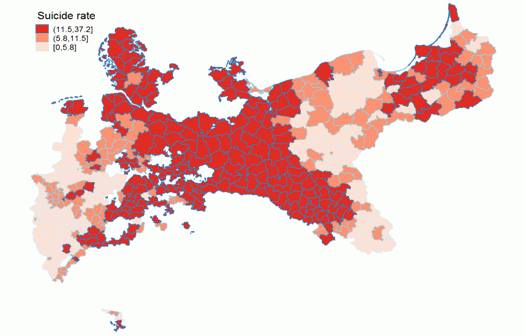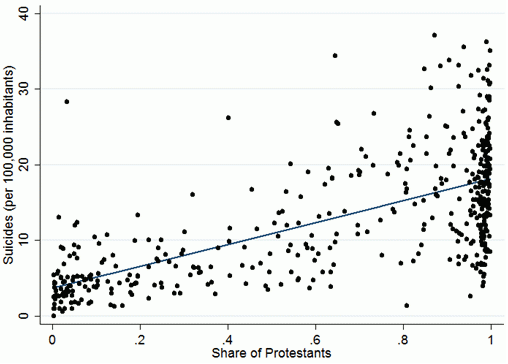Matthew E. Kahn&Matthew J. Kotchen, “Trends in environmental concern as revealed by Google searches: The chilling effect of recession”(VOX, August 21, 2010)
環境問題に対する世間の関心は、奢侈財(ぜいたく品)のような性質を持っているのだろうか? Googleで「失業」と「地球温暖化」という2つのキーワードがどれくらい検索されているかを時系列に沿って調べたところ、景気が後退すると、失業問題への関心が高まるのと同じ分だけ気候変動問題への関心が低下することが判明した。さらには、景気が後退すると、地球温暖化否認論(「地球温暖化なんて起こってない!」)の勢いが強まる場合もあるのだ。
Googleインサイト〔訳注;Googleインサイトのサービスは、現在ではGoogleトレンドに統合されている〕は、Googleのネット検索サービスで特定のキーワードが地域別にどれだけ検索されたかを時系列に沿って調べられるオンラインツールで、誰もが気軽に利用できる。これまでの一連の研究によると、Googleの検索データは、病気の流行(Pelat et al. 2009, Valdiva and Monge-Carella 2010)や経済活動(Choi and Varian 2009, D’Amuri and Marcucci 2009〔拙訳はこちら〕, Varian 2009)の予測に役立てることができる強力なツールであることが明らかになっている。アメリカ経済は、2007年の終盤頃を境にして、1930年代の大恐慌以来最も深刻な景気後退に見舞われたわけだが、Googleの検索データを使って、景気循環と世論との間にどんな関係が成り立っているかを探るのにまたとない機会と言えるかもしれない。
もう少し具体的に突っ込むと、ここ最近のアメリカでは、景気が大きく低迷しているだけでなく、環境問題に対する国民の関心も大いに薄れつつある。景気の悪化(景気後退)は、環境問題に関する世論にどんな影響を及ぼすのだろうか?
そのことについて解き明かそうと試みているのが我々二人がつい最近行ったばかりの研究(Kahn and Kotchen 2010)である。環境問題――その中でも、現在最もホットな争点の一つである気候変動の問題――に関する世論の変遷を跡付けるために、Googleの検索データの助けを借りて分析を加えている。Googleインサイトのサービスを利用して、2004年1月から2010年2月までの間に、「地球温暖化」(“global warming”) と「失業」(“unemployment”) という2つのキーワードがアメリカ国内のそれぞれの州でどれだけ検索されたかを週次データとして集計したのである。そして、その上でこう問うたのである。ある州で失業率が変化すると、その州でのこれら2つのキーワードの検索数にどんな影響が及ぶのだろうか?
その答えはというと、ある州で失業率が上昇すると、その州で「地球温暖化」というキーワードの検索数が減る一方で、「失業」というキーワードの検索数が増える傾向にあったのである。ネット検索(という実際の行動)を通じて顕示された人々の選好に照らす限りでは、景気が後退すると、失業問題に対する関心が高まる一方で――このことは特段驚くことでもないだろう――、環境問題に対する関心が弱まると言えそうである。さらには、これら2つの効果の量的な大きさはほぼ同等であるという興味深い結果も得られている。失業問題に対する関心が高まると、それと同じ分だけ環境問題に対する関心が低下するという解釈も無理なく成り立ちそうなのだ。
赤い州と青い州 ~景気後退に備わるクラウディング・アウト効果がより顕著なのは、どちらの州?~
アメリカ国内では、「赤い州」(“red states”)〔訳注;共和党を支持する傾向が強い保守的な土地柄の州〕と 「青い州」(“blue states”)〔訳注;民主党を支持する傾向が強いリベラルな土地柄の州〕との間で、環境問題をめぐってイデオロギー面での対立があることはよく知られているが、我々の研究では、州ごとの政治的なイデオロギーの違いが、失業率(の変化)とGoogleを使った検索活動(に見られる変化)との間に成り立つ関係にどういった影響を及ぼすかについても検証している。その検証を行うためには、それぞれの州の政治的なイデオロギーの違いを測る必要があるが、2004年の大統領選挙における(民主党側の候補である)ジョン・ケリーの州別の得票率のデータを集めて、それを州ごとの政治的なイデオロギーの違いを測る尺度の一つとして用いている。その検証の結果はというと、民主党寄りの州ほど、失業率が上昇した場合に「地球温暖化」というキーワードの検索数が減る量が大きくて、「失業」というキーワードの検索数が増える量が小さいことが判明した。民主党寄りの州ほど、失業率が上昇した場合に「地球温暖化」というキーワードの検索数が減る量が大きいという結果は、一見すると直感に反するように思えるが、そうなる理由の一つは、共和党支持者は、民主党支持者と比べると、気候変動問題にそもそもあまり関心が無いために、気候変動問題に対する関心が低下する余地が乏しいためなのかもしれない。
失業率が高まると、地球温暖化を否認する声が勢いを増す?
我々の研究では、Googleの検索データ以外にも、アメリカ全土を対象に2度にわたって行われた聞き取り調査――この聞き取り調査では、気候変動問題について同じ質問が問われている――の結果も利用している。聞き取り調査の結果を利用した分析によると、ある州の失業率が上昇すると、その州で暮らす住民が地球温暖化の進行を認める確率が低下し、地球温暖化が進行しているのを認める住民もその意見にどれくらい自信があるかと問われると、失業率が上昇する前と比べると、弱気になりがちであることが判明した。さらには、ある州の失業率が上昇すると、その州で暮らす住民は「米議会は、地球温暖化を防ぐための対策を緩(ゆる)めるべきだ」との意見に傾くという結果も得られている。また、カリフォルニア州で毎月実施されている計11回に及ぶ聞き取り調査――この聞き取り調査では、「’経済’, ‘環境’, ‘仕事’, ‘教育’, ‘健康’, ‘移民’, ‘財政赤字’, ‘税金’, ‘その他’の中で、カリフォルニア州が抱えている一番重要な問題はどれだと思いますか?」という質問が問われている――の結果を利用した分析によると、カリフォルニア州で失業率が上昇すると、「環境」問題をカリフォルニア州が抱えている一番重要な問題だと答える州民の数が大幅に減るという結果が得られている。
Googleの検索データと聞き取り調査の結果を利用した我々の研究は、失業率の変化が環境問題に対する関心に及ぼす影響を実証的に計測した初の試みである。ところで、我々が見出した結果――失業率が高まると、環境問題への関心が低下する――の背後では、どのようなメカニズムが働いているのだろうか? 心理学的な説明を持ち出すと、我々が見出した結果は、マズローの欲求段階説(Maslow 1943)と整合的であり〔訳注1〕、経済学的には、環境問題への関心は奢侈財(ぜいたく品)のような性質を備えていると説明できるだろう。さらには、メディアも原因の一つとして(あるいは増幅要因の一つとして)重要な役割を果たしている可能性もある〔訳注2〕。
メディアの報道との絡みで、以下の2つの図をご覧いただきたい。2006年1月から2010年1月までの間に、メディアで地球温暖化問題と失業問題がどれくらい取り上げられたかを追跡した結果がまとめられている。主要な全国紙での報道を時系列で辿った図1によると、2007年の半ば頃から、地球温暖化問題の取り扱いが減少傾向を辿っていることがわかる。それと時を同じくして、失業問題の取り扱いが上昇傾向に転じていることもわかる。テレビのニュース番組で地球温暖化問題と失業問題がどれくらい取り上げられたかを月間の放送時間数(単位は分)で測った図2によると、2007年11月頃までは、地球温暖化問題も失業問題も放送時間数がほぼ同じくらいであることがわかる。しかしながら、2007年11月以降になると、地球温暖化問題の取り扱い(放送時間数)が次第に減っていく一方で――2009年の終わり頃に、地球温暖化問題の報道が突如として急増しているが、その理由はコペンハーゲンで第15回気候変動枠組条約締約国会議(COP15)が開催されたためである――、景気後退の影響がはっきりと表れ出した2008年の秋頃を境に、失業問題の取り扱い(放送時間数)が大幅に増え出して、その後もずっとその状態が続いていることがわかるだろう。
図1 新聞紙上における「地球温暖化」問題(点線)と「失業」問題(実線)の取り扱いの変遷〔原注;主要な5つの全米紙の記事で「地球温暖化」問題と「失業」問題がどれだけ取り上げられているかを月ごとに集計したもの。データは、Googleニュースでの検索結果を基に作成〕
図2 テレビのニュース番組での「地球温暖化」問題(点線)と「失業」問題(実線)の取り扱いの変遷〔原注;米5大ネットワークで放映されているニュース番組で「地球温暖化」問題と「失業」問題がどれだけの時間取り上げられたかを月ごとに集計したもの(単位は分)。データは、Vanderbilt Television News Archiveでの検索結果を基に作成〕
景気が後退するのに伴って弱まりゆく「政治的な意志」の力
自然環境に対する人々の選好(好み)がどのように形作られるかを理解するためには、さらなる研究が必要とされていることは確かだが、我々の研究は、はっきりとしたパターンの一つを明らかにしている。失業率が高まると――少なくとも、今回の景気後退の最中に経験された高さにまで失業率が上昇すると――、環境問題に対する関心が低下するのだ。我々が見出したこの発見は、景気後退に備わるコストを探る一連の研究に対する新たな貢献という側面も持っている。職を失った労働者や(住宅ローンの返済ができずに)住宅を差し押さえられてマイホームを失った一家が味わう苦しみについてはメディアでも広く取り上げられているし、マクロ経済学者の間でも景気後退に伴う様々なコストについて幅広く論じられている。その一方で、環境経済学の分野に目をやると、景気後退に(銀緑色に輝く)「ほのかな希望の光」(“green silver lining”)を見出す意見も散見される。経済活動が鈍れば、大気汚染が軽減されるというのである(Kahn 1999, Chay and Greenstone 2003)。
しかしながら、我々が見出した結果によると、景気が後退すると、「ほのかな希望の光」を打ち消すような力が作用する可能性があるのだ。失業率が高まると環境問題に対する世間の関心が薄れるようなら、外部性(外部不経済)を内部化するために既存の規制の適用を強化したり新たな環境規制を導入したりするのに必要な「政治的な意志」の力が弱まることになるかもしれないのだ。その実例の一つとしてカリフォルニア州のエピソードを取り上げると、州の失業率が5.5%を下回るまでは州議会下院法案32号(「地球温暖化解決法」)の履行を凍結するよう求める住民投票(「プロポジション23」)が近々実施される予定になっている。アメリカ全土で見ても、野心的なエネルギー・環境規制を導入しようとする動きがここにきて完全に勢いを失っている感がある。ヨーロッパでも同じくだ。ヨーロッパ各国において環境問題への関心と景気循環との間にどのような関係が成り立っているかを探ることは、今後の課題の一つだろう。
〔訳注1〕この点について、この論説の基になっている論文(ジャーナル掲載版)(pdf)では、次のように論じられている。「〔マズローの欲求段階説によると〕、人というのは、生きていく上で欠かせない基本的な欲求が満たされてはじめて、長期的で抽象的な話題に関心を持つようになると見なされている。この考えに従うなら、景気後退の最中においては、気候変動のようなその影響が不確実で長期的な脅威よりも、雇用のような問題に関心が集中するかもしれない」(pp. 258)。「景気後退の只中では、地球温暖化のような抽象的でその影響が不確実な長期的な脅威に対してよりも、その日その日の幸せに関心が注がれる傾向にあるようだ。職を失うかもしれないという恐れ・・・(略)・・・のために、経済の短期的な情勢やマクロ経済の不確実性に関心が向きがちになるのだろう。このような行動パターンは、マズローの欲求段階説と整合的である」(pp. 269~270)。
〔訳注2〕この点について、この論説の基になっている論文(ジャーナル掲載版)(pdf)では、次のように論じられている。「メディアは、国民の関心がシフトするのを予期して、景気後退に関する話題の取り扱いを増やす一方で、気候変動をはじめとした環境問題の取り扱いを減らそうとするインセンティブを持つことになる。・・・(中略)・・・メディアの報道内容は、国民がその都度どんな話題を優先的に重視しているかによって左右されるという意味で、国民の関心を反映している可能性がある。その一方で、メディアは、情報の拡散を通じて国民の関心に影響を及ぼす力を持っていることも認識しておかねばならない」(pp. 270)。
<参考文献>
●Chaoi, H and H Varian (2009), “Predicting the Present with Google Trends(pdf)”, Working paper, Google Inc.
●Chay, K and M Greenstone (2003), “The Impact of Air Pollution On Infant Mortality: Evidence From Geographic Variation In Pollution Shocks Induced By A Recession”, The Quarterly Journal of Economics, 118:1121-1167.
●D’Amuri, Francesco and Juri Marcucci (2009), “The predictive power of Google data: New evidence on US unemployment”, VoxEU.org, 16 December.
●Kahn, ME (1999), “The Silver Lining of Rust Belt Manufacturing Decline”, Journal of Urban Economics, 46:360-76.
●Kahn, ME and MJ Kotchen (2010), “Environmental Concern and the Business Cycle: The Chilling Effect of Recession”, NBER Working Paper 16241.
●Maslow, AH (1943), “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, 50:370-396.
●Varian, Hal (2009), “Doing economics at Google”, VoxEU.org, 8 May, Interview by Romesh Vaitilingam.
●Pelat, C, C Turbelin, A Bar-Hen, A Flahault, and A Valleron (2009), “More Diseases Tracked by Using Google Trends”, Emerging Infectious Diseases, 15:1327-1328.
●Valdivia, A and S Monge-Corella (2010), “Diseases Tracked by Using Google Trends, Spain”, Emerging Infectious Diseases, 16:168.
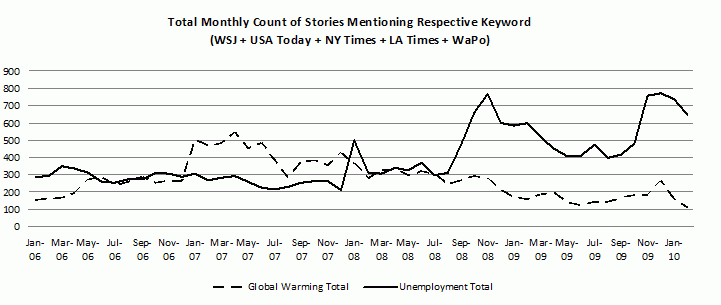
.gif?itok=hAKFiB0P)