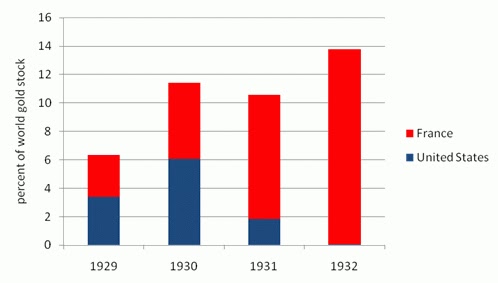「財政ファイナンス」とは何なのだろうか? 本稿では、「貨幣の増刷」、「量的緩和」、「財政ファイナンス」の違いについて説明する。ターナー卿が提案する「財政ファイナンス」が抱える課題――民間の銀行のバランスシートに及ぼす歪み(大量の超過準備の発生)や「中央銀行の独立性」を脅かす可能性――についても触れる。
金融政策についての議論をいたずらに混乱させている2つの用語がある。「貨幣の増刷」と「ヘリコプターマネー」である(Sinn 2011)。
量的緩和≠貨幣の増刷
量的緩和を「貨幣の増刷」(輪転機を回してお金を刷ること)と同一視するのは間違っている。国民によって保有される現金の量は、現金に対する需要によって決まる。(イギリスの中央銀行である)イングランド銀行が量的緩和の一環として民間の銀行から債券を購入すると、その銀行がイングランド銀行に開設している預金口座に債券の購入代金が振り込まれる。つまりは、準備預金の量が増えるというかたちでマネタリーベースの量が増えるが、現金に対する需要は増えない。それゆえ、「貨幣を増刷する(お金を刷る)」必要はないのである。
量的緩和≠ヘリコプターマネー
中央銀行の総裁がへリコプターに乗って、地上で待ち構える国民に向かって空から大量のお金をばらまく。いわゆる「ヘリコプターマネー」というやつだが、量的緩和を「ヘリコプターマネー」とだぶらせるのは、「貨幣の増刷」と同一視する以上に誤解を招く間違いだ。政府であれば、できないことはない。国民に現金を配るか、もう少し現実的な策としては小切手を配布するという手がある――2009年にオーストラリア政府が「キャッシュ・スプラッシュ」(“cash splash”)と命名された小切手を多くの納税者に配布した例がある――。しかしながら、それは金融政策ではなくて財政政策だ。中央銀行は、国民に現金を配る権限を持ち合わせていないのだ(中央銀行に可能なのは、資産を交換することだけである。量的緩和がまさにそれにあたる)。国民に現金を配るためには、その他の財政政策と同様に、議会での予算編成プロセスを通じて承認を受ける必要がある。ヘリコプターからお金をばらまけるのは政府なのであり、政府がお金をばらまくのは財政政策なのである。
「ヘリコプターマネー」が総需要を刺激するのにどれくらい効果的かについては意見が割れている――どのような政策についても、意見が割れるものだが――。クラウディング・アウトがそれほど起きなかったり、リカードの中立命題が当てはまらないようなら――需給ギャップが存在していて、金融政策によって金利が低く抑えられているようなら、クラウディング・アウトもそれほど起こらないだろうし、リカードの中立命題も当てはまりそうにない――、「ヘリコプターマネー」が総需要を刺激する可能性は高いだろう。あるいは、財政赤字を埋め合わせるために低金利で借り入れをする(国債を発行する)ことができるようなら――今がまさにそのような状況である――、「ヘリコプターマネー」が総需要を刺激する可能性は高いだろう。突然の施し(現金)に恵まれた国民は、一部を貯金するかもしれないが、ほとんどを支出するだろう。総需要を刺激する上で量的緩和よりも「ヘリコプターマネー」の方が確実性が高い方法と言えそうである。
財政ファイナンス
財政赤字を賄うために国債を発行したら金利が上昇してしまうかもしれなかったり、国債に買い手がつかなかったりするおそれがあるようなら、中央銀行が財政赤字を賄うという手がある。中央銀行が新発国債を買い取って、政府が中央銀行に開設している預金口座(政府預金)に代金を振り込むのだ。政府が主導権を握る場合もあるかもしれないが、このような「財政ファイナンス」は量的緩和の一種だと言える。
「財政ファイナンス」のコストを負担することになるのは誰なのだろうか? 中央銀行に新発国債を買い取ってもらったおかげで増えた政府預金を原資として、政府が国民に小切手(「キャッシュ・スプラッシュ」)を配布したら、その小切手は民間の銀行に持ち込まれるだろう。国民が欲するだけの現金を既に手元に持っているようなら、小切手を換金してもそのまま預金口座に預け入れるだろう。最終的にどうなるかというと、国民が民間の銀行に預ける預金(民間の銀行にとっての債務)が増えて、民間の銀行が中央銀行に預ける預金(民間の銀行にとっての資産)が増えるだろう。すなわち、民間の銀行が「財政ファイナンス」のコストを負担することになるのだ。保有する準備預金の量が増えるというかたちで。
「財政ファイナンス」は公的な債務を増やさないかというと、そうじゃない。中央銀行が民間の銀行に対して負う債務(準備預金)が増えるからである。準備預金に対して市場金利と同じ水準の金利が支払われるようなら――大半の国でそうなっている――、財政赤字の調達コストが節約されることにもならない。中央銀行が準備預金に対して市場金利を下回る金利を支払うようなら、財政赤字の調達コストが節約されることになるが、民間の銀行に課税しているに等しい。
「財政ファイナンス」と通常の量的緩和とは違いもある。一つ目の違いは、通常の量的緩和であれば、タイミングなり金額なりについて中央銀行が単独で決めるが、「財政ファイナンス」であれば、タイミングなり金額なりについて中央銀行と政府が共同で決めるところである。そこで問題になるのが、「中央銀行の独立性」である。政府による乱費を防ぐためには、政府が財政赤字の補填を要求してきた時に中央銀行が「ノー」と言えることが肝心だが、「ノー」と言えなくなってしまうかもしれないのだ。二つ目は、いつ終わるかについてのマーケットの理解に違いがあるところである。通常の量的緩和については、いつかの時点で必ず終わるに違いないというのがマーケットの共通理解だが、「財政ファイナンス」については、いつ終わるかがはっきりしないのだ(民間の銀行が大量の超過準備の保有を強いられる状況が長続きしそうにないことだけは確かだが)。
アデール・ターナー卿がインフレ警戒論者と財政規律論者に批判を加えているが(Turner 2013)、もっともだ。貨幣と物価の関係について時代遅れの考えを引きずっているインフレ警戒論者も間違っているし、需給ギャップが存在しているのに財政刺激策の無効性や有害性を説く財政規律論者も間違っている。しかしながら、ターナー卿が提案している周到な「財政ファイナンス」案の是非を判断するには、その便益だけでなく、弊害――量的緩和ならびに「財政ファイナンス」が民間の銀行のバランスシートに及ぼす歪み(大量の超過準備の発生)や「中央銀行の独立性」を脅かす可能性――にも目を向ける必要があるのだ。
<参考文献>
●Sinn, Hans-Werner (2011), “The threat to use the printing press”, VoxEU.org, 18 November.
●Turner, Adair (2013), “Debt, Money and Mephistopheles: How do we get out of this mess?”, speech, Cass Business School.